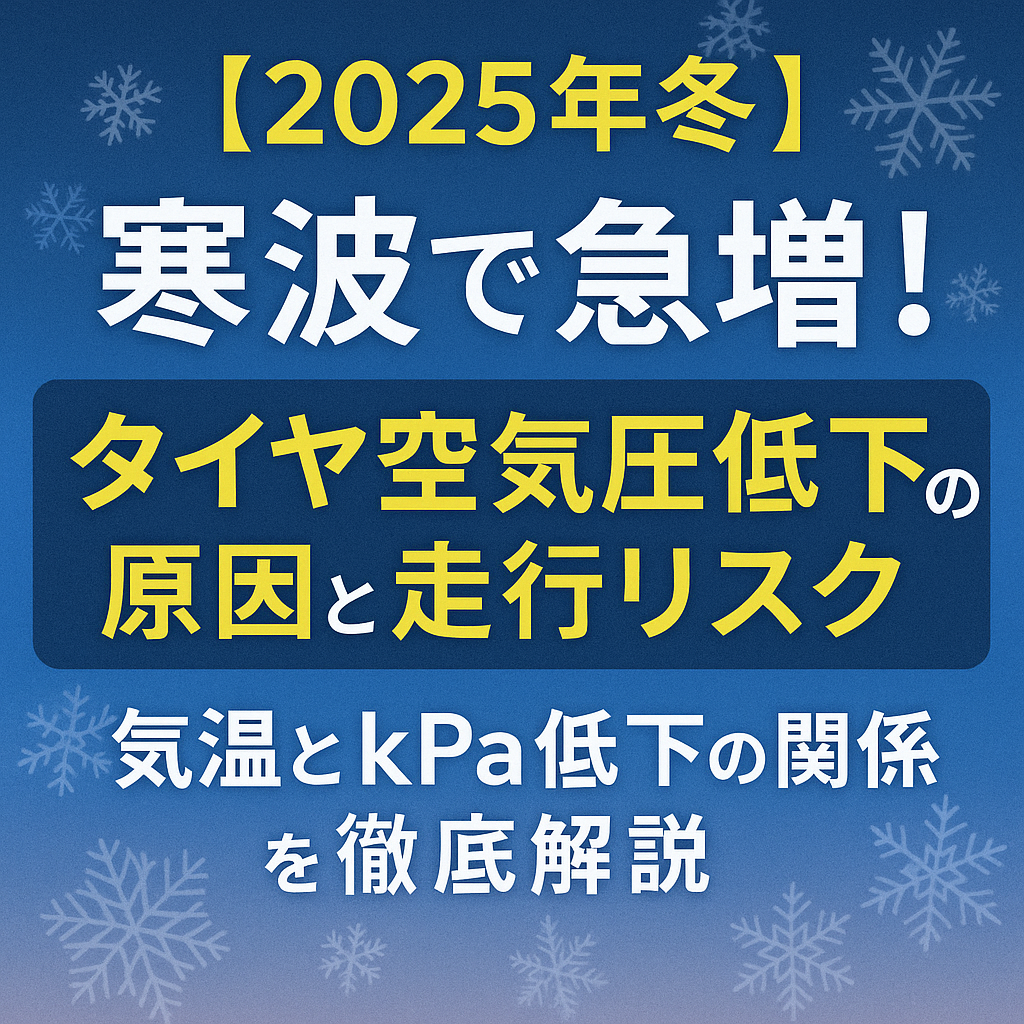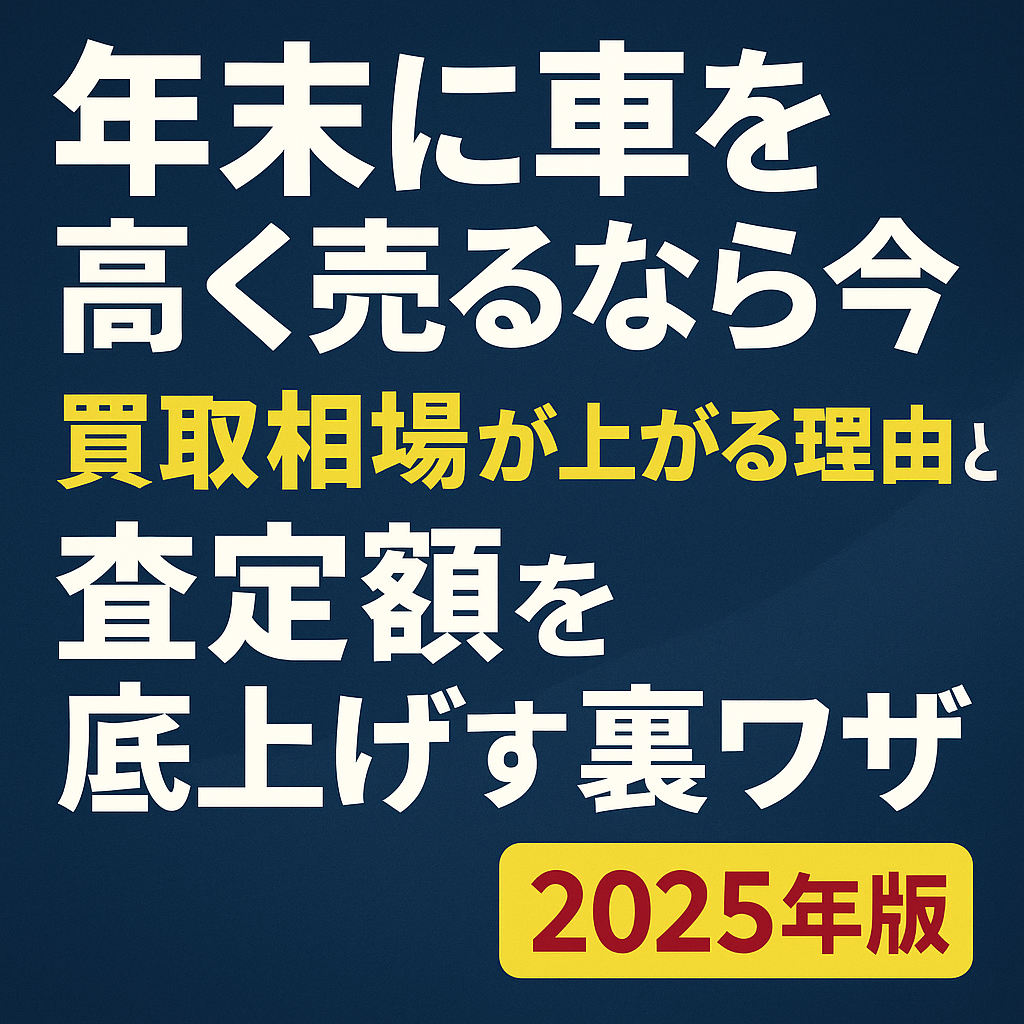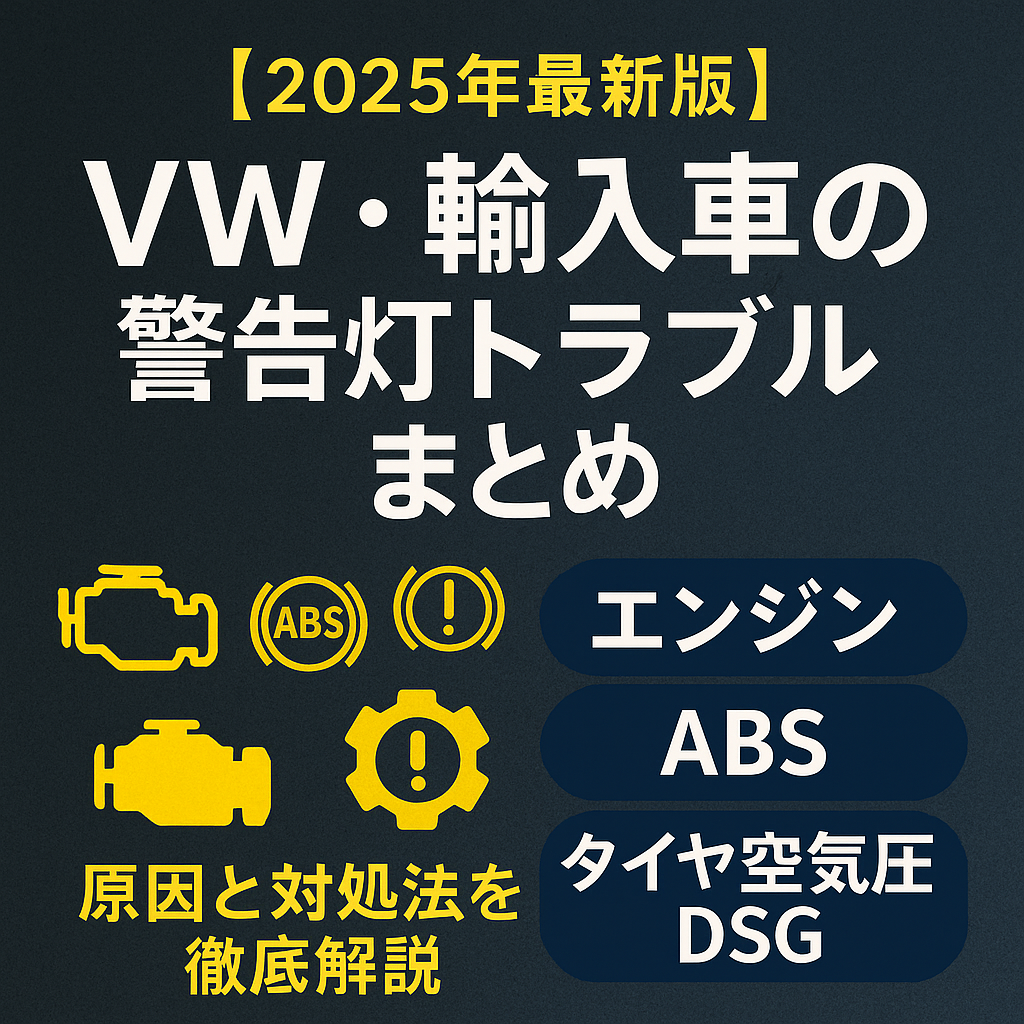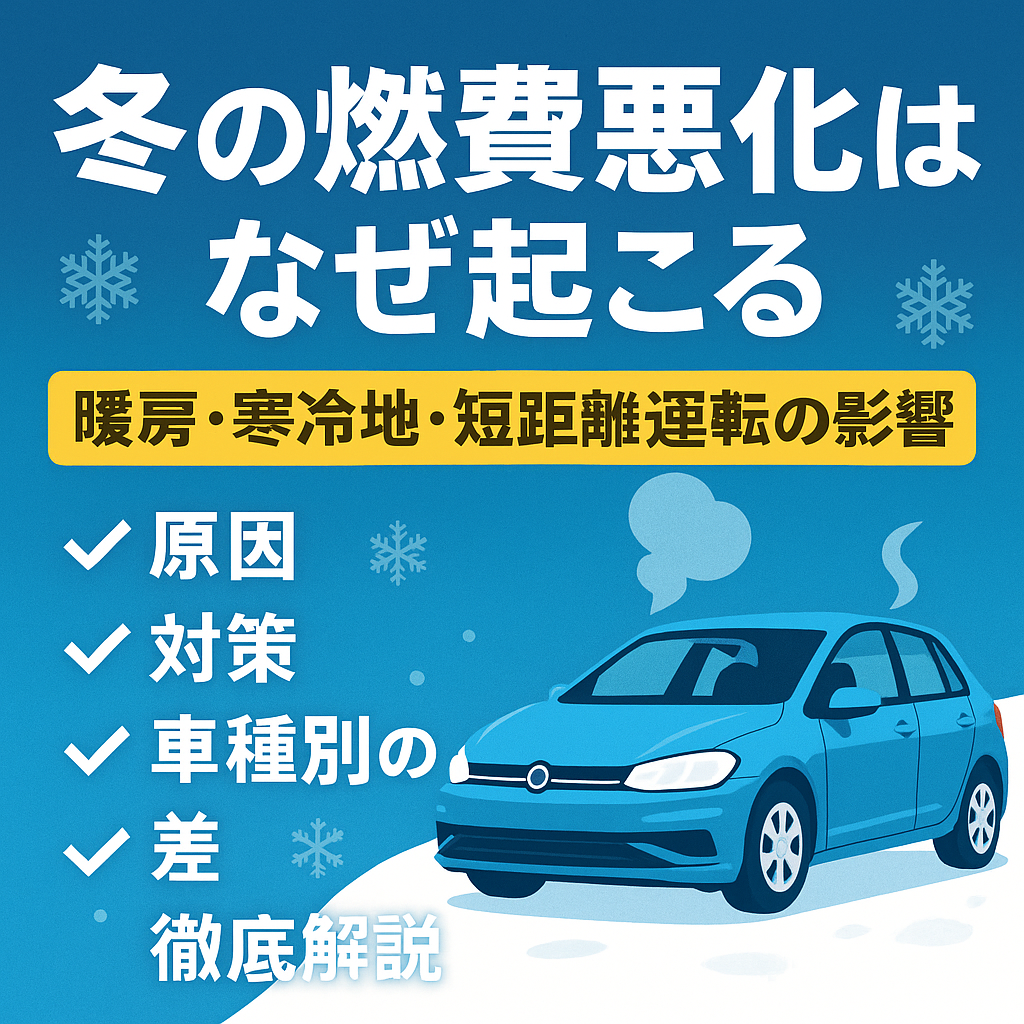なぜ輸入車はハイオク指定が多いのか?欧州車と日本のガソリン事情の違い

2025年夏、ガソリン価格の高止まりが続くなか、多くのドライバーが燃料費の負担を感じています。特に輸入車オーナーにとっては、ハイオク指定車が多いことで一層の出費が懸念されます。しかし、なぜヨーロッパ車を中心とした輸入車はハイオクガソリンの使用を前提としているのでしょうか?その理由を、ガソリンの性質や国際的な基準の違いを踏まえて解説します。
ガソリン価格はどうなっている?2025年7月の実態
経済産業省・資源エネルギー庁が2025年7月16日に発表したデータによれば、同年7月14日時点の店頭現金価格は以下の通りです。
- レギュラーガソリン:173.2円/L
- ハイオクガソリン:184.0円/L
- 軽油:153.4円/L
ハイオクはレギュラーよりも10円ほど高い価格設定が一般的です。長距離通勤や頻繁な運転が必要な人にとっては、この差が年間で数万円の差につながることも。
ハイオクとレギュラーの違いは「オクタン価」
レギュラーとハイオクの違いは、主に「オクタン価」にあります。これはガソリンの自己着火しにくさを示す指標で、値が高いほどノッキング(異常燃焼)が起きにくくなります。
エンジンは燃料と空気を混ぜた混合気をピストンで圧縮し、スパークプラグの点火で爆発させて動力を得ます。この際、ガソリンが自己着火しやすいと、意図しないタイミングで燃焼が起こり、エンジンの損傷やパフォーマンス低下につながることがあります。
ハイオクはこのリスクを避け、より高い圧縮比での燃焼を可能にするため、高性能車には必須の燃料とされています。
国産車と輸入車の燃料指定の違い
日本車の多くはレギュラーガソリン仕様です。軽自動車からファミリーカーまで、ほとんどの車がレギュラーで設計されています。ただし、日産「GT-R」やトヨタ「GRスープラ」など、一部のスポーツモデルではハイオクが指定されています。
一方、輸入車はハイパフォーマンスカーに限らず、コンパクトカーでもハイオク指定が主流です。たとえば、フォルクスワーゲン「ポロ」、プジョー「208」、ルノー「ルーテシア」など、欧州では日常使いされるモデルですら、ハイオクを指定しています。
なぜコンパクトな輸入車でもハイオク仕様なのか?
これは、各国におけるオクタン価の基準と流通するガソリンの質の違いに理由があります。
日本ではJIS規格により、オクタン価が「90」のものがレギュラー、「100」のものがハイオクとされることが多くあります。一方、ヨーロッパでは「95」や「98」のガソリンが一般的で、「92」以下の低オクタン価ガソリンはほとんど使われていません。
つまり、欧州車は95以上のオクタン価を前提にエンジン設計されているため、日本で販売される際には「日本のハイオク」でなければ性能が発揮できないのです。
アメリカとの違いもある
アメリカでは「87」「89」「91」などのオクタン価のガソリンが使われていますが、表示方法が日本やヨーロッパとは異なります。平均法(RON+MON)/2の方式を採用しているため、一見低いように見える数値も、実際の品質は欧州の「91~95」と同等とされています。
日本のガソリン事情とエンジン技術の進化
日本が産油国でないという事情から、石油精製においてできる限り効率良く製品を分配する必要がありました。その結果、オクタン価の低いレギュラーを主流とし、それに合わせた高効率なエンジン開発が進められたのです。
この背景により、日本車のエンジンはレギュラーガソリンでも十分な燃費と出力を発揮できる技術力を備えるようになりました。
日本のハイオクは欧州より高品質?
日本のハイオクガソリンは、オクタン価が「100」であることが多く、欧州の「98」よりも高い数値となっています。1980年代後半から輸入車ユーザーの間で高オクタン価のガソリンが好まれるようになり、石油各社もそれに応じて高品質のハイオクを供給するようになったという背景があります。
ガソリンの品質はオクタン価だけでなく、洗浄剤や添加剤の有無なども関係していますが、当時は「高オクタン=高品質」というイメージが強く定着していました。
まとめ|ハイオク指定には理由がある
輸入車がハイオクを必要とするのは、単に高性能だからという理由だけでなく、エンジン設計時点での燃料想定が欧州基準であるためです。日本のレギュラーではオクタン価が不足しており、本来の性能が発揮できないどころか、エンジンへの悪影響すら考えられます。
燃料費を抑えるには、あらかじめ燃料指定をチェックして車選びをするのがポイント。また、輸入車であっても、近年ではレギュラー仕様のモデルも増えてきているので、選択肢として検討するのも良いでしょう。
高騰する燃料価格と向き合う今だからこそ、燃料の違いとその意味を理解することは、賢いカーライフの第一歩となるはずです。

 この記事をお気に入り
この記事をお気に入り